揺さぶられっ子症候群
6月9日、北陸もついに梅雨に入りしました。うっとうしい季節です。イネ科花粉の数も、最近は10個以下と低迷しています。スギからイネへの春の花粉症も、そろそろおしまいのようです。
子ども達の間では、胃腸炎や高熱を伴う風邪、水ぼうそうが流行っています。気圧や気温も不安定で、喘息発作も出やすい季節です。
さて、今月のマンスリーニュースは、雑誌を読んでいて気になった話題についてお話します。
(1)揺さぶられっ子症候群
最近読んだ週間朝日(6月9日号)に「揺さぶられっ子症候群が増えている。」と、赤ちゃんを扱う時の注意を喚起していました。
「泣きやまない赤ん坊を親が揺さぶるようにしてあやすのは、よく見られる光景だ。しかし、まだ首がすわっていない乳児を強く揺さぶったことが原因で赤ちゃんが脳内出血を起こしてしまう『揺さぶられっ子症候群』が最近相次いで報告されている。」とその冒頭に述べられています。
1974年、アメリカの医学会で報告されたのが最初ですが、その後も各国で報告されています。
赤ちゃんの頭は、身体の割合から見ると大きい(重い)ため、外傷を受けた時に他の部位に比べて外力を受けやすいのです。特に、首の座ってない不安定な時期には、脳内の組織や血管が未熟で、強く揺すぶられることによって、むち打ち運動に対して弱い脳内の血管が切れて出血してしまいます。出血によってけいれんや意識障害、さらに出血が強度の場合には死亡することも(25〜50%)、まれではありません。命が助かっても、後遺症として視力障害、運動麻痺、難聴、てんかん、知能学習障害などが残ることもあります。
泣きやまないわが子は優しく揺すって寝かしてください。イライラして、強く揺すり過ぎると逆効果だけでなく、危険が伴うことを頭に入れておきましょう。専門家は、1歳半頃までは注意と話しています。
(2)医療の原点に戻ろう
これも最近のこと、「日本医師会ニュース」のプリズム欄に、「医療の原点に戻ろう」という表題で一文が寄せられていました。
「先日、患者さんを診察中、腹部の触診をしていたら、『先生、おなかを触って何かわかるんですか』と聞かれた。『このごろ、おなかを触る医者はおらんですよ』と突然いわれて、一瞬とまどった。
『おなかの診察で、器械では分からない、皮膚の色とか温かさとか硬さや塊や胃腸の動きが分かって、診断に役立つんですよ』と説明したのだが、近ごろの医師たちは検査はよくするけど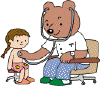 、身体診察はあまりしないというのは本当なのだろうか。患者さんをよく理解するのに、器械を介した接触や会話だけでは十分でないだろう。触診する指先の感覚、手のひらの感じが、聴診器の伝える音と共に、患者さんとの結びつきを無言のうちに強めているのではないだろうか。」
、身体診察はあまりしないというのは本当なのだろうか。患者さんをよく理解するのに、器械を介した接触や会話だけでは十分でないだろう。触診する指先の感覚、手のひらの感じが、聴診器の伝える音と共に、患者さんとの結びつきを無言のうちに強めているのではないだろうか。」
まったく同感です。私の専門とする小児科では、お腹の触診はとくに大切です。
まだ、私が卒業して小児科医になって5、6年目のころ、一人医長で能登の病院へ赴任したことがありました。ある時、私は学会への出張があるため大学から代診の先生に来ていただいたことがあります。たまたま、以前私が診察したことのある赤ちゃんのお腹に何か腫瘤があると診断された代診の先生は、患者さんを金沢の小児外科へ紹介されました。診断は、「先天性尿管拡張症」でした。診察した時間のズレはありましたが、私がもう少し丁寧に診察していればもっと早くと悔やまれました。
大学で勤務していた時、教授の診察を見ながら「お腹の触診は念入りにしないといけないんだな」と教えられていたにもかかわらず、いつの間にか惰性に流されていたのです。
開業してから、一人の白血病のお子さんに出会いました。小さいころ小児喘息で診察に通っておられた患者さんです。久しぶりに顔色が悪いと言って受診されたのですが、お腹を触ると肝臓や脾臓があふれんばかりに腫れていました。学校検診など、何かの折りにお腹を触っていれば・・・と悔やまれました。現在そのお子さんは、発病後5年を過ぎて、幸いにも元気で学校に通っておられますが、早く見つかるに越したことはありません。
福井にいる私と同年代の友人に遅い子どもが授かったとき、「お腹を触ってくれる小児科医を見つけろよ」とアドバイスしたのは当然のことです。